|
(35)お庚申様
お庚申様(おこうしんさま)というのはご存知でしょうか?
これは古くからある日本の民間信仰で、「庚申待(こうしんまち)」「庚申講(こうしんこう)」とも呼ばれ、庚申の日に神仏を祀って徹夜をする行事のことです。今ではあまりやらなくなってしまった行事ですが、神社やお寺では、「庚申塔」や「庚申堂」というものが、その名残として残っています。
さて、この庚申の行事の意味ですが、これは道教や陰陽道に由来し、人間の頭と腹と足に「三戸の虫(さんしのむし)」という、常にその人の悪事を監視している虫がいるといわれ、この虫が庚申の日に限って、人間が寝ている間に天上界に上り、天帝(閻魔大王ともいうらしい)に、その人のすべての行状を逐一報告し、その内容によっては寿命が縮められたり、死後に地獄・餓鬼・畜生の三悪童に堕ちるといわれていたのです。
このスパイ虫に日ごろの行いを報告されないようにするにはどうしたらいいか?ということで、この虫が抜け出す庚申の日は、一晩中起きていれば虫が抜け出せないという考えから始まったのが「庚申講」や「庚申待」といわれる行事です。
庚申の日の夜、寺社の庚申堂に集まり、お神酒や精進料理を供えて、祭事をし、その後飲食をしながら一晩過ごしたのが、「庚申講」や「庚申待」といわれるものです。古くは「枕草子」にも庚申待の話が登場しますが、江戸時代に入ってから民間に広まった信仰のようです。今では廃れてしまいましたが、庚申の縁日や村の親睦を兼ねた集まりとして、庚申待を行っている地方もあるそうです。
そういえば、コブメロん家のお寺にも古そうな庚申塔があって、小さい時から「今日はお庚申様だよ」なんて耳にしていました。どんな行事をやっていたのかはあまり記憶にないですが、私の実家付近の地域では、今もまだ庚申の行事をやっているようですね。
この庚申待については、冷泉天皇の女御で、三条天皇の生母の藤原超子(とおこ)が、庚申待の明け方に脇息に寄りかかったまま眠るように亡くなっていたという話も残されています。(漫画、陰陽師でも出てましたね)
さて、この虫が身体から抜け出し、何かを報告に行くという話は日本の古い信仰話ですが、現在のスピリチュアルでも、人は寝ている間にアストラル体が抜け出し、あちらの世界に行ってエネルギーの充電や情報交換をして、また肉体に戻ってくるといわれていますね。ひょっとしたら、このシステムのことを昔の人は知っていて、これを虫が抜け出すという表現にしたんだろうか?などと考えてみました。あちらの世界では、何でもかんでもお見通しということから、「悪事がばれる」と解釈したのかな?なんて^^;
それともう一つ、人は身体のアチコチが痛くなることがありますが、腰の痛みが治ったかなと思うと、今度は肩が痛くなったり、なんて経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。肩の痛みが肘に移動して、手首にきて治まった、なんて話も聞いたことがあると思います。
この身体のあちこちに移動する痛みは、もしかしたら三戸の虫が身体の中を移動しているのかも?なんて考えてみちゃいました。小さい子供の疳の虫とかもこの虫の仕業なのかしら〜?
庚申待の行事は、江戸時代より一般庶民の間でも盛んに行われたようですが、一晩かけて虫が出て行くのを阻止するという宗教的な行事より、どちらかというと「一晩飲み明かすぞ〜!」という村の人たち同士の親睦会のような、飲み会のような側面もあったようです。
現代では珍しいものとなってしまった庚申待ですが、昨今のスピリチュアルに興味をお持ちの皆さんで、この庚申待を再現してみるのも面白いかもしれないですよ。庚申待ちをしながら一晩中スピリチュアルについて語り明かすなんてのはどうでしょう〜(^^)

この絵は、おゲレツ、おバカ映画で有名な「オースティン・パワーズ」。こんな彼は英国の秘密諜報部員なのです。下品な映画だと思われているかもしれないですが、音楽やファッションは気が利いていて、楽しくていい映画ですね☆
<東三河エネルギー研鑽会の日常 2008年7月14日ブログ記事より>
 目次へ戻る 目次へ戻る 
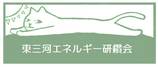
|